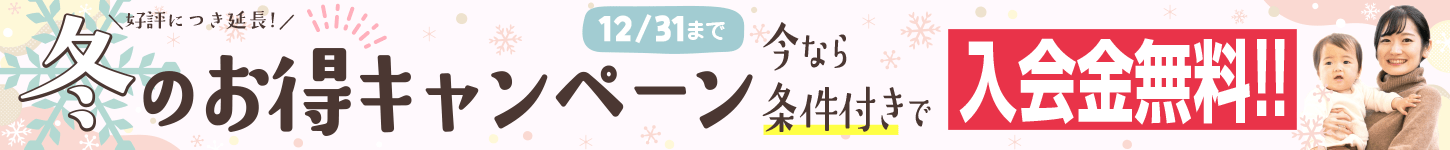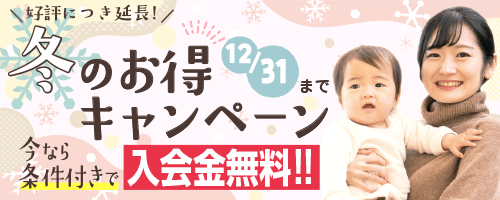【幼児教育の豆知識】中学受験に向いている子と向かない子の特徴は? 受験させる必要性についても徹底解説!

年々加熱している中学受験。マンガやドラマで中学受験がテーマのものを目にすることもあり、「中学受験って大変そう。うちの子に受けさせるかどうか迷ってしまう」と悩んでいるお父さん、お母さんもいるのでは。
そこで今回は、中学受験に向いている子、向いていない子の特徴を解説。中学受験のメリットやデメリットもまとめています。受験が必要かどうかを考える参考にしてくださいね。
Contents
中学受験に向いている子と向かない子
どんな子どもが中学受験に向いているのでしょう。逆に向いていない子とは?それぞれ特徴をまとめました。
中学受験に向いている子の特徴
まずは、中学受験に向いているとされる子どもの特徴を見ていきましょう。
精神年齢が高く、ある程度自立している子
中学受験に向けては、スケジュール管理や遊ぶのを我慢して机に向かう自制心、合格へ向けてのプレッシャーや緊張に打ち勝つ精神力が求められます。ただ、小学生ではまだ自分の欲求に負けてしまったり、自己管理ができなかったり、ということも。
その点、同年齢の友だちよりもやや大人びた考え方をする、しっかりと自分の意見が言え、多くの場面で感情のコントロールができる、といった精神年齢が高めの子は、受験にとっては有利と言えるでしょう。
言われたことを素直に聞ける子
親の指導やアドバイスに対して素直に応じられる子どもも、中学受験に向いています。中学受験は親がある程度導いていくもの。特に低学年、中学年のうちは家庭での学習の管理もしてあげなくてはなりません。それに対して反発する我の強い子どもは、勉強の進みが遅くなってしまうかもしれません。
夢や目標をしっかり持っている子
将来なりたい職業があり、そのために「この中学校に行く」といった目標を持っているならば、受験勉強にも自発的に取り組めるでしょう。逆に親が「この学校を目指しなさい」と決めてしまうと、「やらされている感」で最後まで息が続かないかもしれません。
今後の進路についてはきちんと親子で話し合い、子どもと一緒に目標を定めるようにするといいですね。
好奇心が旺盛な子
中学受験の勉強内容は通常の小学校の授業とは大きく異なり、多くの知識や特殊な計算法などを習得しなくてはなりません。中学校進学後も、一般の公立校よりもハイレベルな授業が待っています。
それについていけるのは、自分から学び、ものごとを探求していく好奇心が旺盛な子ども。内容を深掘りせず、知識や公式をただ詰め込むだけの勉強は苦痛であり、長続きしないでしょう。
スピード感のある考え方や行動ができる子
制限時間内で効率よく確実に点数を取れるように、問題の難易度をさっと見極め、テンポよく説いていくことが求められる中学受験。考えるのに時間がかかりがち、一題解くのもゆっくり、ということでは高得点は望めません。
つまり、「スピード感のある考え方・行動ができる」というのも重要なポイントなのです。会話の切り返しが早い、問いかけられたことに対してすぐ回答する、思い立ったらすぐ行動する、といった特徴が子どもにあるならば、中学受験に向いていると判断できます。
体が丈夫な子
フィジカル面での強さもメリットとなります。受験対策の塾は夜遅くなることも多く、家での勉強時間も長くなると、ときに睡眠時間を削られることも。体が弱くすぐに体調を崩してしまうようでは勉強も滞りがちになってしまいます。
冬季が本番の受験においても体力は必須。風邪をひかない、ひいてもすぐに回復する、連日続く受験にも耐えられる。そんな強さがあれば、落ち着いて受験に向かうことができます。
周りの子とあまりなじめない子
少し変わっていて、公立小学校でなかなか周囲となじめずに苦労した、という子は、中学受験を選択するのがベターかもしれません。受験校は偏差値だけではなく、校風や教育方針を選んで進学する子どもたちも多いため、価値観の合う友だちに出会える可能性は高いと言えます。
また、公立校にはない専門的で高度なカリキュラムを取り入れている学校もあります。子どもが興味のある分野に力を入れている学校を選べば、よりその才能を伸ばすことができるでしょう。
中学受験に向かない子の特徴
一方で、中学受験に向いていない、という子はどんな特徴があるのでしょうか。「向いている子」の裏返しでもあるのですが、その中からいくつかをピックアップして解説していきます。
成長が遅く、親がいないと何もできない子
精神的にやや幼く、勉強や生活の管理で親のサポートが欠かせない、という子は、受験勉強も一人で進めるのは困難。将来の目標を考えるにも至らず、受験へと自分の気持ちを向けられないかもしれません。
ウソをついてごまかしてしまう子
課題を考えずに解答を写して提出する、まだ理解できていないのに先生に「わかった」と言って切り上げるなど、ウソをついて面倒なことや困難なことをごまかしてしまう子も問題です。
高学年になるとウソも巧みになってくるので、親が気づかないうちに周囲からぐんと遅れてしまっていた、といったことになりかねません。
学校の勉強がかんばしくない子
そもそも小学校で学ぶ内容が理解しきれていない場合は、さらに複雑な中学受験の勉強には歯が立ちません。無理に受験勉強をさせると、周囲に比べて理解できないことが多く、劣等感を植え付けてしまう危険性も。まずは小学校の勉強についていけるようにケアしてあげることが大切です。
勉強や受験にはまったく興味がない子
そもそも勉強嫌いで遊んでばかりの子を、受験に向かわせるのは難しいもの。まずは苦手意識を取り除き、学ぶ基本姿勢を作っていくことから取り組まねばなりません。
また、勉強ができる子でも自発的に受験したいと考えるとは限りません。興味がないようであれば、目標とする中学校の魅力を共有し、「受験したい」と自ら思えるように導いていく必要があります。
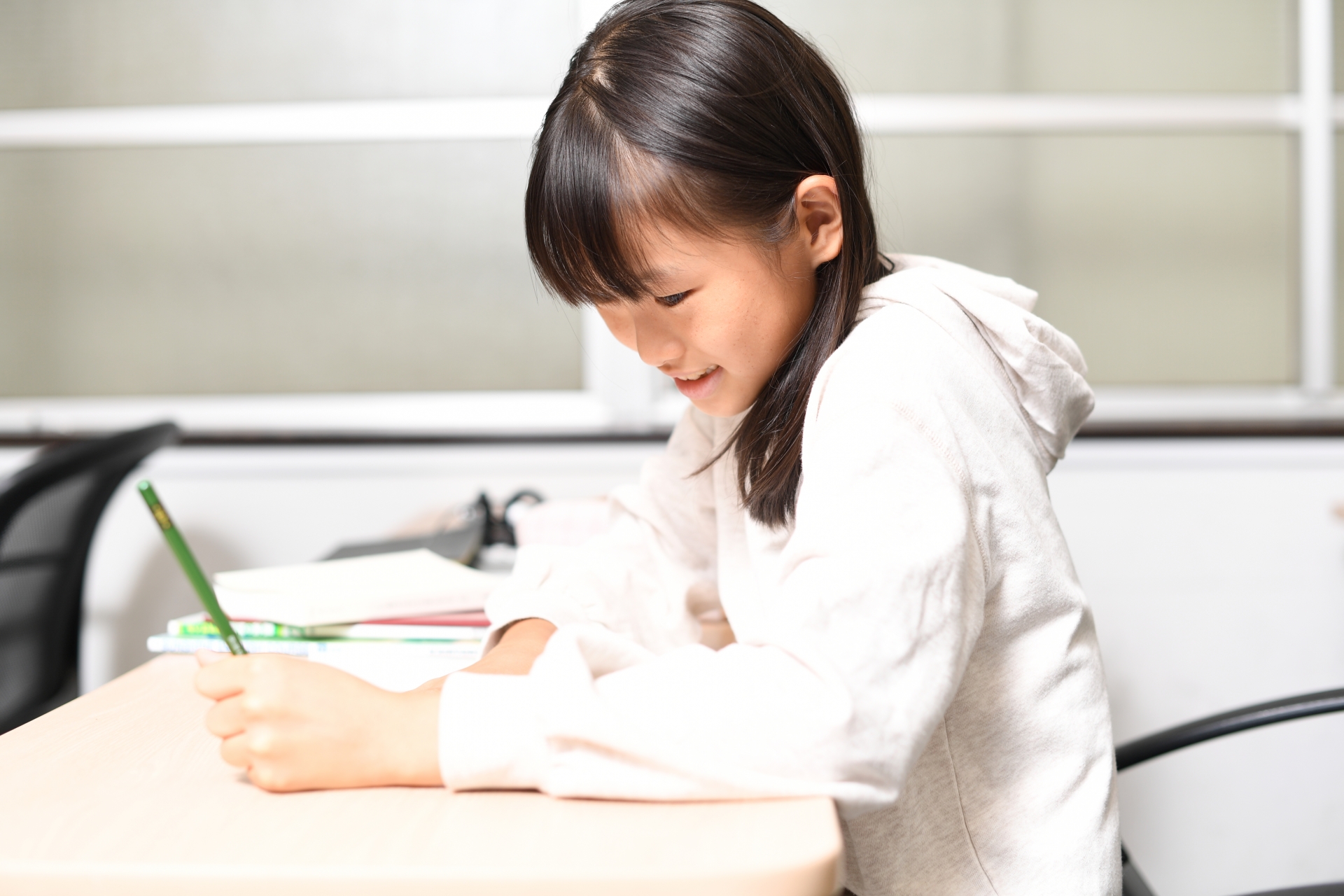
中学受験に向かない子を無理に受験させてはいけない
上記のような特徴が自分の子どもに見受けられるようであれば、中学受験について再考したほうがいいでしょう。子どもの特性を無視して無理やり受験勉強に向かわせたとしたら、合格どころか次のようなダメージを負ってしまう可能性もあります。
・学ぶことが嫌いになってその後も放棄してしまう
・必死で合格しても中学校の授業についていけず不登校になる
これらは体験者の声の一例です。「子どものため」と受験を押し付けるのではなく、子ども特性をよく見て、必要かどうかを判断していかなくてはなりません。
子どもの心身の成長スピードは個人差が大きいもの。中学校受験には向かなくても、中学校の3年間で大きく成長し、自分で努力して高校受験に取り組める可能性ももちろんあります。
「絶対中学受験をしなくてはならない」「中学受験に向いていないからダメだ」という思い込みは捨て、わが子の特性を理解してその成長に合わせた進路をともに探していくことが重要です。
中学受験に向かない親の特徴
中学受験は親のサポートが欠かせないもの。親の取り組み姿勢や考え方は合否にも影響します。中学受験に向かない親の特徴を把握し、まずは父母の考え方から変えていきましょう。
受験に対して夫婦の足並みがそろわない
目標校の設定はもちろん、塾の選択や家での勉強の仕方など、父母の意見が異なると子どもも混乱してしまいます。
受験をするかどうかの前に、「子どもにどんな人生を歩んでもらいたいのか」「そのためにはどんな教育環境を与えたいか」といったことから話し合い、夫婦で意見を一致させたうえで子どもに親の意図を伝えましょう。
家族が一体となり子どもを支えてあげることで、長い受験の道のりも歩ききることができるのです。
子どもに結果だけを求めて追い込んでしまう
受験勉強の途中には、思うような点数が取れないなど壁にぶつかることもあるでしょう。そんなときに、テストの点数だけで子どもを責めたり、褒めたりといった態度を取ると、「点数を取れなければ自分には価値がない」と子どもの自信を奪ってしまうことに。
また、学校のブランドや進学実績だけを気にして、「ここに合格できなければあなたは失敗」といったことを言い続けるのも、子どもを追い詰める原因になります。
努力しているプロセスを褒め、たとえ望む学校に手が届かなかったとしても、チャレンジしたことを認めて新たなステージへと背中を押してあげましょう。
そもそも中学受験は必要なのか
「中学受験に向く向かない」というテーマで解説してきましたが、前提として、そもそも中学受験はしたほうがいいのか、なぜ中学受験をするのかという根本的なことを考えておくことが必要です。
そのためにはまず、判断材料となる中学受験のメリットとデメリットを知っておきましょう。
中学受験のメリット
まずは、中学受験をした場合のメリットについて考えてみます。目標とする中学校に進学できるだけではなく、がんばって取り組んだ経験は子どもにとって大きなプラスとなります。
子どもの内面を成長させる
数年間受験勉強を続けることで、自分で学習のスケジュールを立て、ときに遊びたい気持ちをコントロールしつつ勉強を進める「自立心」が育っていきます。そうして得た学習習慣は、中学校以降も子どもの財産に。
また、「目標に向かってやりきった」という体験は、万が一合格に届かなくても、その後の人生において困難を乗り越える自信となることでしょう。
将来の大学進学が有利になる
有名大学の進学実績が多い中学校に入学すれば、相応の質の高い教育が期待できます。
また、大学附属の学校であれば推薦でスムーズに進学できる可能性が高く、将来の受験競争を早期に回避することができるでしょう。そうすれば、中学・高校と自分のやりたいことに思う存分打ち込めるはずです。
子どもに合った環境を選べる
偏差値が高い中学校に入学するためだけが、中学受験ではありません。子どもに合った教育環境を選べるのも受験の大きなメリットです。
私立をはじめとした各中学校は、さまざまな特色を打ち出しています。教育方針だけではなく、施設やクラブ活動などもそれぞれ異なります。子どもの性格ややりたいことなどに合致した学校を見つけられれば、自分らしくのびのびとした学生生活を送ることができるでしょう。
中学受験のデメリット
メリットがある反面で、デメリットもいくつかあります。受験をするかどうかを決める際には、これらのデメリットも知ったうえで覚悟を決めて臨みましょう。
勉強嫌いになってしまう恐れがある
例えば塾に週3回、家庭学習を平日2~3時間、休日だと7、8時間など、中学受験をするとなると普段の生活が勉強中心になります。意欲を持って楽しんで取り組める子はいいのですが、場合によっては勉強漬けの毎日や親からのプレッシャーのため、勉強嫌いになってしまう子どもも。
挫折により、自信を持てなくなる可能性がある
模擬試験で思ったような判定が出なかったり、難易度の高い勉強についていけなくなったり。そういった挫折を繰り返し体験すると、「どうせ自分は合格なんてできない」と自信をなくしてしまうことも考えられます。
親の精神的・経済的負担が大きい
親にとってのデメリットといえば、受験対策の高額な費用です。受験塾の費用や交通費はもちろん、模擬試験の費用、長期休暇中の補講や特別講座の費用、場合によっては家庭教師の費用などで、小学4年生~6年生まで約300万円かかったという人も。それに加え、受験料も1回につき2~3万円が必要です。進学後も、私立中学校の場合は公立に比べ高額な学費を払い続けることに。それだけの経済的余裕があるかを、具体的に考えておかねばなりません。
さらに、合格へ向けてサポートしていくという精神的な負担もあります。他の子の成績が気になったり、わが子の成績に悩んだりすることもあるでしょう。親があせって暴走してしまうと、子どもにプレッシャーをかけすぎるなどして親子関係が悪化してしまうケースもあるのです。
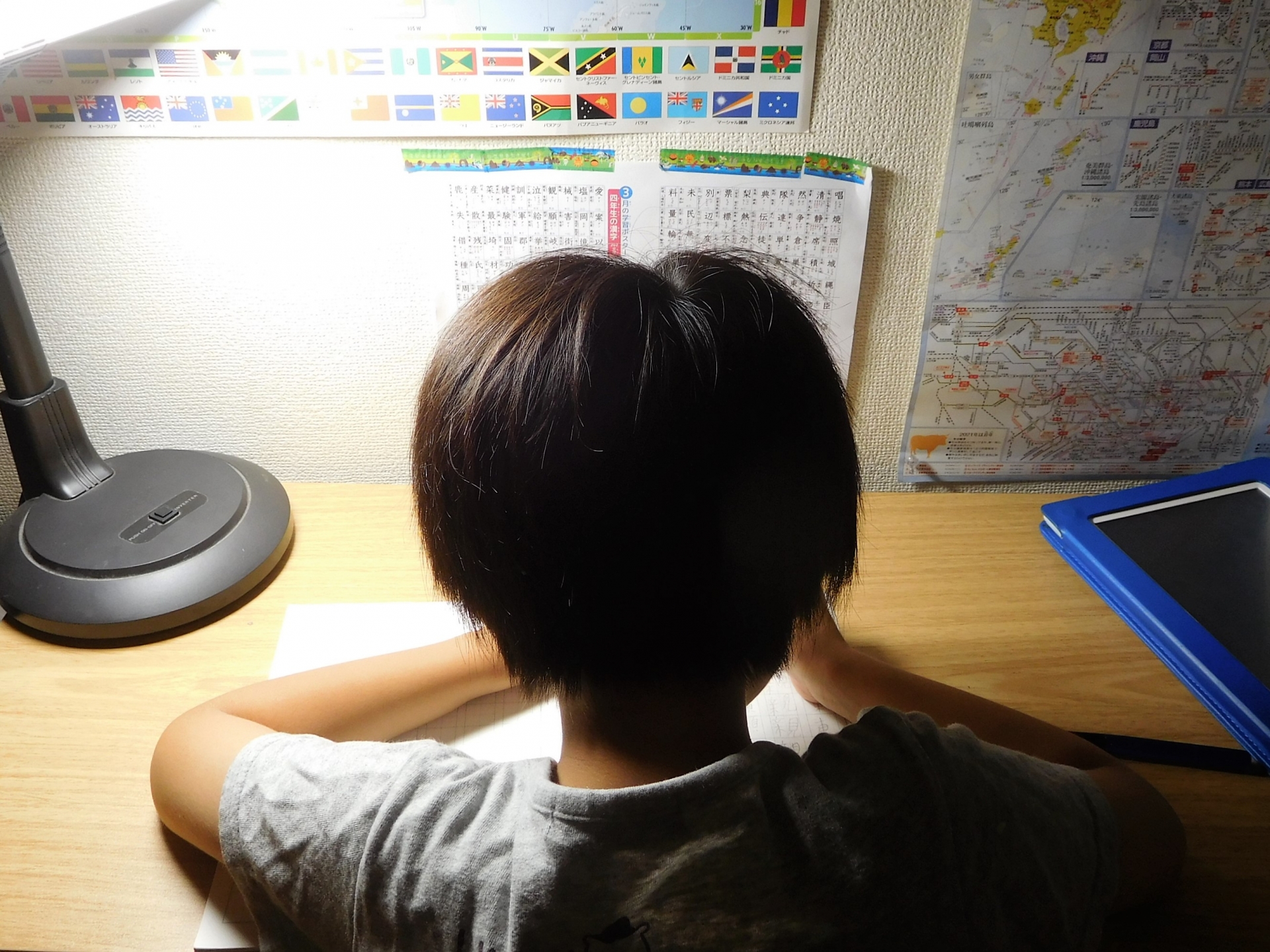
中学受験で親が気を付けるべき3つのポイント
子どもにとって大きなチャレンジである中学受験。親の関わり方が結果に大きく影響することは、これまでの解説でお分かりかと思います。改めて、親はどのような点に気を付けて中学受験に臨めばいいのか、主な3つのポイントを押さえておきましょう。
受験を無理強いしない
まだ遊びたい盛りの子どもたちにとって、長時間机に向かうことは簡単ではありません。受験勉強がつらくなり、「もう辞めたい」言い出すことも十分に考えられます。
そのときに、「今まで塾に通って勉強してきたのにもったいないから」「ここでやめたらあきらめるクセがついてしまうのでは」などと思い、厳しくしかりつけて無理に受験勉強を続行させてしまうとどうなるでしょうか。
子どもがいうことをきいたとしても恐怖心からであり、自分を苦しめる親への信頼は失ってしまいます。嫌々なので成績も上がらず、そればかりか一度失った信頼関係を回復するには長い年月がかかるでしょう。
先述したとおり、中学受験に向かない子もいます。わが子の特性をよく見て、「やめさせるのが適切な判断」と思ったら、潔く受験をあきらめることが肝要です。
親の思い込みは捨てる
「まだ子どもだから、親がすべてを決めてあげなければならない」「いい中学校に入れるのがこの子の一番の幸せ」と、親の思い込みで勝手にものごとを進めてしまうことは避けましょう。幼くとも、きちんと子どもの意見を聞いてあげることが大切です。
「仲のいい友だちと一緒に地元の中学校に行きたい」といった子どもなりの意見もあるでしょう。成長していくにつれ考え方も変わっていくので、定期的に子どもと話し合い、目標を共有して受験準備を進めていきましょう。
各校の資料を集めて違いを説明してあげたり、進路の考え方を示してあげたり、子どもが自分の希望をまとめられるように広く選択肢を示してあげられるといいですね。
何よりも大切なのは親子関係
中学受験でもっとも重要なのは、親子の良好な関係です。子は親の愛情と支え、あたたかい励ましに対して、がんばろうと思えるのです。
ましてや、小学校高学年は思春期、第二次反抗期に入ってくる時期。ただでさえ複雑な心情を抱えているところに、「勉強しなさい!」と常に小言ばかり言う、テストの点数しか気にしない親では、反発こそすれ努力する気持ちは失ってしまいます。
まずは親が子どもを信じ、コントロールするのではなく自身の力で進むのをサポートしてあげること。そしてその表情や言動から気持ちを察し、適切に声掛けをしてあげることです。
そのためには、幼いころから十分にコミュニケーションを取り、わが子のことをよく知ろうと心掛けることが大切です。

まとめ
子どもの適性をしっかり見極め、受験のメリット・デメリットを十分に理解したうえで臨むことが大切
中学受験は、子どもはもちろん親にとっても大きな決断です。「とりあえずチャレンジする」ということではなく、メリット、デメリットを親子ともに理解してから決めるようにしましょう。
大切なのは、子どもが「入学してよかった」と思える中学校に進むということ。目標とする学校は親の欲で選ぶのではなく、わが子に適しているかどうかという視点で検討を。子ども自身が「入学したい」と強く思うことができれば、受験へのチャレンジはきっと人生の糧となるでしょう。
中学受験をしてもしなくても「後伸び」可能なヘーグル教育
幼児教室ヘーグルには「中学受験対策講座(MEP)」もあり、たくさんのも大きな成果をあげていますが、中学受験期は人間形成においても、とても重要な時期。ヘーグルでは受験で無理に引っ張ることは一切しません。子どもの伸び方を最優先して、土台となる力をつけていくことに注力しています。
だから、ヘーグルの子どもたちの多くは、中学受験より、さらに高い偏差値の大学に進学しているのも大きな特徴。
ヘーグルで幼少期から「素地力(土台となる力)」を身につけているので、本人が本気モードになった時に思う存分力を発揮することができるようになっているからです。いわゆる「今伸び」「後伸び」ができるヘーグル教育、ご興味ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

株式会社ヘーグル 代表
「波動読み」を世界で初めて開発。小学校受験 中学受験、高校受験、大学受験生の指導経験もあり、 幅広い経験の中で醸成される幼児からの右脳教育プログラムは、奥が深く、確実に成果の出るものとして絶賛されている。

【執筆者】逸見 宙偉子(へんみ るいこ)
株式会社ヘーグル 代表
「波動読み」を世界で初めて開発。小学校受験 中学受験、高校受験、大学受験生の指導経験もあり、 幅広い経験の中で醸成される幼児からの右脳教育プログラムは、奥が深く、確実に成果の出るものとして絶賛されている。