右脳開発でお子様の才能を開花


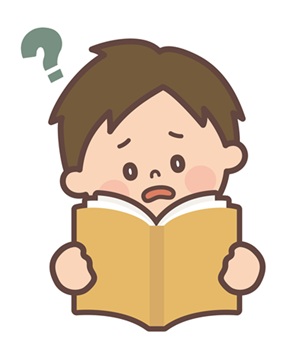 これからますます
これからますます
AIが浸透していく時代に
必要な能力とは何でしょう。
それは国語力です。
当然、算数・数学力は必要ですが、
見落としてしまいがちなのは
この力です。
英語も大事ですが、
英語を優先し過ぎて
国語力が不足してしまうという
事態は避けたいものです。
ChatGPTから始まったAI時代には、
“プロンプト”つまり
AIにどのような指令を出すのか、
AIから出てきた成果物を
どう修正、校正そして推敲、
ファクトチェックをするのかは、
最終的に人間がやらなくては
なりません。
AO大学入試も
小論文と面接は必要ですし、
社会に出ても国語力は必須です。
それでは、
小学生のうちに国語力を伸ばし、
中学受験でも通用する
読解力を育てる方法を
考えてみましょう。
中学受験の国語では、
長文読解の正確さが
求められます。
「文章は読めるけれど、
正しい答えを選べない」
「記述問題で点が取れない」
というお悩みをよく聞きますが、
これは単なる読書習慣だけでは
解決しづらい問題 です。
では、どのようにすれば、
子どもの読解力を
確実に伸ばせるのでしょうか?
具体的な方法を5つご紹介します。
1. 音読を習慣にする
「目で読む」だけでなく、
「声に出して読む」ことで
理解を深める
音読には、
「文章の構造を意識する」
「リズムよく読むことで
内容を理解する」
「語彙力を増やす」
という効果があります。
ポイントは、
ただ読むのではなく、
意味を考えながら読むこと!
物語文なら、
登場人物の気持ちを込めて読む
説明文なら、
「大事なところはどこか」
を意識しながら読む
音読後に、
「どんな話だった?」
と子どもに要約させる
このような習慣をつけるだけで、
文章を「聞いて理解する力」と
「自分で要約する力」が
身についていきます。
2. 読んだ文章の「要点」を
まとめさせる
「なぜそうなったの?」
を考える習慣をつける
読解力がある子は、
「文章の流れ(論理構造)」
を意識して読めるという
特徴があります。
その力を養うために、
読んだ文章を簡単なメモや図に
まとめる練習をしましょう。
物語なら、
「①どんな出来事があった?
②登場人物の気持ちは
どう変化した?」を整理
説明文なら、
「①主題(筆者が伝えたいこと)
②理由 ③具体例」をまとめる
最初は親が一緒にやり、
少しずつ自分でできるように
促していきましょう。
3. 記述問題に取り組む前に
「口頭で答えさせる」
書く前に「話す」ことで、
思考力を鍛えられます。
記述問題が苦手な子は、
「何を書けばいいのかわからない」
「答えがぼんやりしている」
ことが多いのです。
まずは、口頭で説明させる
練習から始めましょう。
「この文章の大事なところを
1文で言うと?」と聞く
「どうしてそう思うの?」
と理由をたずねる
親子で会話しながら、
答えを整理する
話すことで、子どもは
考えをまとめやすくなり、
記述問題にも強くなります。
そして、稚拙でもいいから
“とにかく書いてみる”
ことです。
書くことによって、
学力の基盤が養われます。
4.日常会話で「言葉の意味」を
意識させる
語彙力が読解力のカギ!
国語の読解問題が
苦手な子の多くは、
「言葉の意味がわからない」
ことが原因です。
たとえば、
「効果的な方法は?」
「筆者の意図は?」
と聞かれたときに、
「効果的」「意図」という
言葉の意味がわからなければ、
答えられません。
語彙力を伸ばすには、
普段の会話の中で
「言葉の意味」を
意識させることが大切です。
難しい言葉が出てきたら、
「○○ってどういう意味だと思う?」
と聞いてみる
ニュースや本の中の言葉を
一緒に調べる
類義語・反対語を考えさせる
(例:「効果的」の反対は?)
この習慣がつくと、
自然に語彙が増え、
読解問題でも意味を正しく
とらえられるようになります。
そして、
辞書とお友達になることも
大切です。
引いたことのあるページに
付箋を貼ったり、
ラインマーカーを引かせ、
全ページにラインマーカーが
引いてある辞書を作りましょう。
5. 親子で「一緒に問題を解く」
時間を作る
解答のプロセスを共有し、
「なぜその答えになるのか」
を考えさせる
子どもが問題を解いたら、
「丸付けして終わり」ではなく、
親も一緒に考える時間を
作ることが重要です。
間違えた問題は、
解説を読む前に
「なぜこの答えを選んだの?」
と聞いてみる
「どこに答えのヒントがあった?」
と文章の中で探させる
「もし違う答えを選ぶなら、
どれを選ぶ?」と考えさせる
このやりとりを続けることで、
子どもは「問題の解き方」を理解し、
読解の精度が上がります。
中学受験で通用する
国語の読解力を身につけるには、
日々の積み重ねが不可欠です。
「たくさん本を読んでいるのに、
読解問題が苦手…」という子も、
読み方のコツを意識すれば
必ず伸びます!
ヘーグルのカリキュラムは、
幼児の時期から一貫して
子どもの国語力の基盤が
養成できるように作られています。
1.「せんがきおけいこ」
から始まり
「S1、S2プリント」
2. プレ小学部レベルⅠ(年中)から
始まる「心の話」、
プレ小学部レベルⅡ(年長)で行う
「読解力・発表力養成講座」
3. 小学1年生から始まる
Pre-MEPⅠ・Ⅱでの
「国語力読解力養成講座」と
「ジュニア人間学」
4.小学3年から始まる
MEPアネックスでの
「課題図書」と「記述課題」
5. 小学4年から始まる
MEPウィークリー、
特にアドバンス(5年)では、
「詳細読解力養成」、
「論理力養成講座」
「要約プリント」
「記述課題講座」
「文法力養成講座」等で
一生使える国語力の
基盤となる力を養成しています。
MEPを卒業した生徒たちは、
「中学以降、特に勉強しなくても
国語の点数はいい」とか、
「論文で賞をとった」など、
確実に国語力の基盤ができたとの
報告が数多くあります。
ぜひ、ヘーグルのカリキュラムで
お子様の国語力の基盤を
作ってあげてください。